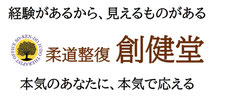文責 柔道整復 創健堂 院長 榊原孝文
いつまでも健康でありたい
誰もが願うことで、私も同じです。
『病気にならないように、予防が大切』
『病気の早期発見・早期治療』
重要なことだとは思うのですが、下の図を見てください。
厚生労働省が公表している「主要死因別死亡率(人口10万人対)の長期推移(~2016年)」のデータをグラフにまとめたものです。
2016年までのデータで死亡率が高いのは
1位 悪性新生物
2位 心疾患
3位 肺炎
4位 脳血管疾患
5位 老衰
となっています。
この中で大幅に増えているのが、悪性新生物(がん)と肺炎です。
しかし、市民健診・企業健診・がん検診など、予防や早期発見が大切といって検査が推奨され、それにより検査を積極的に受けて、異常が見つかれば早い段階から治療を受けているのに、なぜ死亡率が下がらず逆に増えてしまうのでしょうか。おかしいですね!?
医療を受ける目的は、『良くなる為』のはず、、、
良くなるはずが、思うようによくならず、逆に
病気をこじらせて命を落とすのはイヤ!ですよね。
私も同じなので、いろいろと調べてみました。そうしたらいろいろなことが分かったんです。
☟☟☟☟☟☟☟☟☟ 重要
「自分の健康については、積極的に知識を得て、病気になった時にはどのような治療を受けるのか、またどんな治療は受けないようにするのかを自分で決める」
☝☝☝☝☝☝☝☝☝ 重要
これからお伝えすることが、あなたの参考になれば幸いです。
誤解を受けないようにあらかじめお話しますが、私自身が、がんを告知され早く死にたくないから、がんに関することを調べてみて、そして分かったことを、私と同じように望んでいる方にお伝えしようとしているだけで、私の考えを押しつけようというのではありません。
がんが恐ろしいといわれる理由として、あちこちに転移する、際限なく大きくなる、病気の進行とともに痛みが強くなりやがて耐えられないほどになるというようなイメージがあるからではないでしょうか。
しかし、実際はそうではないようです。経験のない私にとっては、その情報は書籍によるしかないのですが、以下に何冊かの書籍を紹介します。
著者
中村 仁一 :京都大学医学部卒業、財団法人高尾病院院長・理事長を経て2000年2月より社会福祉法人老人ホーム「同和園」付属診療所所長、医師
近藤 誠 :慶応義塾大学医学部卒業後、同大学医学部放射線科入局。83年から同大学医学部放射線科講師。がんの放射線治療を専門とし、乳がんの乳房温存療法を積極的にすすめる。また、医療の情報公開にも力を注ぐ。

この書籍は、中村医師と近藤医師が対談しそれを書き起こしています。この中で次のような記述があります。
・・・
がんが痛むのではない。治療で痛む
中村医師:
しかも、がんは世間で思われているほど痛まない。がんがここまで嫌われ、恐れられる大きな理由は、麻薬を使っても時には抑えきれないほど強烈な痛みや苦しみを伴い、のたうちまわって死ぬと思われているからでしょう。
痛みが強調されすぎて、痛まなかった人たちが表に出てこないから、みんな「がんは痛むもの」と思い込んでいるんですよ。僕も病院に勤務していたころはご多分にもれず、「がんは最期は絶対に痛むもの」と思っていました。
近藤医師:
老人ホームで認識が変わられたんですね。
中村医師:
病院勤務のころは、がんを放置した例は一例もなかったんです。「治療する」ことを期待されてたから。本人も家族も「治療は当然やるもんだ」と思っているから、「治療しない」というのはマイナスで、とても受け入れてもらえないですからね。
しかし患者はみんな、手術で痛んだり、抗がん剤で苦しむわけです。「むかつく」とか「髪の毛が抜ける」とかいろんな症状が出るってことは、抗がん剤がその人にすごい悪影響を及ぼして、ひどい負担で、体が「やめてくれ」って悲鳴をあげているということでしょう。風邪薬ではありえないことですよね。
また、治療の結果の痛みを、当人もまわりも「がんの痛み」だと思い込んでしまう。
僕もそう思い込んでいました。老人ホームに移って、強烈な痛みを伴うのはがんのせいじゃなく、治療のせいなんだとよくわかりましたよ。
・・・
いくらでも見つかる「潜在がん」「がんもどき」
近藤医師:
「潜在がん」という病変があります。生前症状がなくほかの原因で亡くなって解剖してみて、初めてわかる。この潜在がんはいろいろな臓器にかなりの頻度で見つかります。たとえば50歳を超えた男性の2人に1人は、死後解剖すれば前立腺がんが見つかる。けれども、それは放っておいても大きくならない「潜在がん」なんです。
また、わずかな病変まで検出できる方法があったら、日本人の3人に1人は甲状腺がんと診断されるでしょう。でも甲状腺がんで亡くなる人は、すべての死亡数のわずか0.1%。日本人が甲状腺がんで亡くなるのは1000に1つです。
詳しく検診するほど、がんはいくらでも見つかります。でもその大部分が、命を奪わない潜在がんか「がんもどき」です。放っておいても大きくならないか、消えてしまうがんです。
・・・
死ぬまで痛みを感じさせなかったがんがあるというのです。
放っておいても大丈夫な「潜在がん」?「がんもどき」って何?
そもそも「がん」とは何ぞやということですが・・・
がん細胞は、元々は正常だった細胞が、遺伝子に異常が起こることで細胞分裂(増殖)の働きに歯止めが利かなくなってしまい、際限なく増殖し続ける性質をもってしまった細胞です。
そして、元のところにとどまらず他の臓器に転移し増殖する可能性があるものです。
近藤医師は下記の書籍のプロローグで、次のように記述しています。

著者
近藤 誠 :同前
・・・
読者は、がんは恐ろしいと思っているだろう。最期は痛く、苦しむ病気だと。しかしそれは多分に、手術や抗がん剤の副作用で苦しむ患者から作られたイメージなのだ。がんは本来、意識を保ちながら穏やかな最期を迎えることができる病気である。僕は老化のひとつと考え、病気で死ぬなら、がんが良いと思っている。もちろん、ときには、がんによる痛みや苦しさが生じることもある。だが、それらは、緩和ケアによって和らげることができる。
ぼくは「がん放置療法」を提唱しているが、一切の治療をしないと言うのではない。必要なときには、痛みを取り、苦しみを和らげる治療をする。最小限の治療が、最良の治療なのだ。
今、日本で行われているがん治療の多くは不必要なものである。不必要な手術、不必要な化学療法(抗がん剤)、不必要な放射線治療。
・・・中略・・・
医者による不要な医療を断り、不利益から逃れるためには、患者・家族自身が医療業界の現状や医療システムの欠陥を知って、自衛するしかない。医療システムの欠陥は今や大学病院にとどまらず、日本の医療全体に深く根を張り、むしばんでいる。人口減少化時代を迎え、医療産業はますます患者を欲している。医者につける薬はない。医療産業のお得意様にならぬよう、患者自身が学んでほしい。その一助になるよう、本書を著すことにした。
2014年3月、ぼくは慶應病院を定年退職した。40年間、大学病院で行ってきた診療と研究によって確信できたことを、ここに記したい、
がんが恐ろしいのではない。がん治療と、それを行う医者たちが恐ろしいのである。
・・・
目からうろこ・・・と思うのは私だけ!?
また、、、

この書籍では、次のように記述しています。
・・・
「がんもどき」で人は死なない
まず、「本物のがん」と「がんもどき」についてまとめておきます。
がん細胞はウイルスでもなくインベーダーでもなく、「身内」です。タバコ、大気汚染、農薬、放射線などの発がん物質によって遺伝子が傷つき、自分自身の正常細胞が変異して、がん細胞が生まれます。
がんの性質は、ヒトの性質と同じようにさまざまです。
しこりがどんどん大きくなるがん。変わらないがん。小さくなるがん。消えるがん。上皮内(粘膜の最上層)にとどまるがん。インクがにじむように周囲に広がるがん。種をばらまくように広がるがん。もぐりこむように粘膜の下の層まで達するがん。
リンパ節に転移するがん。遠くの臓器に転移するがん。転移しないがん・・・。
しかし、僕の分類では、がんは「臓器転移のある本物のがん」か「転移のないがんもどき」の2つに1つです。
「本物」と「もどき」は、細胞を顕微鏡で見ても瓜二つ。しかし、顔がそっくりで見分けがつかない「ワル」と「いい人」がいるように、全く性質が違います。
話題のiPS細胞と同様に、無限に自己をコピーし異種の細胞も作りながら増え続ける性質をもつ「がん幹細胞」が次々に見つかっています。「iPS細胞とがん細胞は、表裏」と、開発者の山中伸弥・京都大学教授自身が語っています。
「本物」か「もどき」かは、幹細胞によって決まります。幹細胞は、組織のおおもとになって性質を決める細胞。がん幹細胞が生まれた瞬間に、そのがんの性質が、決まっているわけです。
「本物のがん」は幹細胞が生まれてすぐ、人間には見つけられない0.1ミリ以下のときから、血液にのって全身に転移し始めることを、臨床データが教えてくれます。
人間が「早期発見」と呼んでいるのは、実はしこりが1センチ前後に育った「がんの晩年」。幹細胞が生まれてから10~30年もたち、がん細胞は10億個にも増えて、転移がひそんでいる状態です。10億個すべてが、もとの幹細胞の性質を受け継いでいます。
だから、本物のがんは、いわゆる「早期発見」でいくら切り取っても、モグラたたきのように再発する。
メスの入った傷口にがん細胞がワッと取りついて「がんが暴れる」こともあります。
「本物のがん」は、人を殺すがんです。その特徴として、
①無限に増大する。②多臓器に転移する。
この2つの性質を、兼ねていることがあげられます。
「がんもどき」には転移能力がなく、大きくならなかったり、自然に消えることもよくあります。おとなしくて、人を殺せるほどの勢いがないわけです。
・・・
「本物のがん」は見つかった時にはすでに転移していて、いくら切り取っても再発する。「がんもどき」は転移能力がなく、大きくならなかったり、自然に消えることもある。
そして、がんが痛むのではなく治療で痛むとしたら、見つかったからといってすぐに治療するというのではなく、充分に検討する必要がありますね。
だって、痛い思いをするのは自分なんですから・・・
がんの治療といえば、三大療法が主なものです。
①手術療法
②化学療法(薬物療法)
③放射線療法
①の手術療法は、文字通りがん組織を切除してしまう方法ですが、病巣部分だけでなく転移を防ぐという理由から周囲のリンパ節(免疫にかかわる組織)まで、大きく取り除く手術が行われます。
さらに転移を防ぐ目的で、②の化学療法(抗がん剤治療)が併用されます。
②の化学療法は、抗がん剤という薬物を点滴、注射、内服という方法で体内に入れ効果を期待する方法です。
抗がん剤は『際限なく分裂するがん細胞の遺伝子を傷つけて、細胞分裂を起こさせないようにすることでがん組織を委縮させる』目的で使われます。
下のイラストでは、火災現場に向かう消防車と、すでに現場に駆けつけて消防活動を行う消防士が描かれています。

消防士は火事現場に到着してから放水を始めます。これは当たり前の行動です。出火していないところに放水すれば、余計な被害を出してしまいます。
しかし、薬はそういうわけにはいきません。
抗がん剤に限らず薬は全てそうですが、薬の効果(期待する働き)と副作用(不要な働き)を現す成分は、血流に乗り全身を巡ります。そして、あちこちに大なり小なりの影響を及ぼしながら流れていって、患部に到達した成分が目的の効果を発揮することで症状・状態の改善がみられるんですね。
イラストでいえば、消防車が現場に向かって走っている間、ずっと水をまき散らしているのと同じだということです。
抗がん剤が遺伝子を傷つけるのは、がん細胞だけではありません。正常な細胞の遺伝子にも傷をつけて増殖を阻害します。抗がん剤治療を受けている人の髪の毛が抜けたり、感染症にかかりやすくなるのも、毛母細胞の細胞増殖や、免疫で働く白血球の増殖が阻害されるためです。
また、抗がん剤の副作用には「発がん性」があります。
抗がん剤を取り扱う医療従事者に向けたこちらの資料を読み進めてみて下さい。
難しい言葉を飛ばして読んだとしても、抗がん剤の危険性は十分に理解できると思います。
抗がん剤治療を奨められた場合は、このような副作用があることを理解した上で、受けるか受けないかを決めることが大切なのではないでしょうか?
抗がん剤でがんは治るの?
抗がん剤が有効とされる基準は以下のようになっています。
1.がんの大きさが3分の2になる。
2.その縮小が1ヶ月持続した。
3.上記の1と2の該当者が、全被験者の10~20%いればいい。
この3つの基準を満たせば、有効と判断され、日本の厚労省は抗がん剤として認可するので実際に使用されるようになるのだそうです。ここには「がん組織が消滅する」という基準項目はありません。
また、使用した患者が数か月後に薬の副作用で亡くなったとしても「有効」グループにカウントされたままになるそうです。
③の放射線療法は、放射線を使ってがん細胞の遺伝子を破壊し、がん細胞の増殖を妨ごうとするのが目的です。
しかし、原発事故で問題になっていますが、放射線には発がん性があります。正常細胞の遺伝子が放射線によって傷つけられるからです。
身体の深いところにある、がん組織に放射線を照射しようとすれば、皮膚からがん組織の間に介在する正常細胞がその影響を受けます。
手術のように体を傷つけない放射線療法だから大丈夫というわけではないのです。
ちなみにCT検査やマンモグラフィー検査も放射線が使われます。定期健診などで被ばく線量が多ければ、発がん確率は高くなりますよね。
もう一度考えてみませんか?
早く見つけられているはずの「がん」の死亡率が、上昇してしまうのはなぜ?
取扱い上とても危険な薬が、患者にとっては大丈夫?
安易に放射線を被ばくしていいの?
この他にも参考になる書籍を紹介します。
著者
宇田川久美子:薬剤師、栄養学博士

著者
長尾和宏:医療法人社団裕和会理事長、長尾クリニック院長、医師、医学博士

著者
安保 徹(故人):新潟大学大学院医学部教授

著者
安保 徹(故人):新潟大学医学部教授
石原結實:医学博士、イシハラクリニック院長
福田 稔:医師、日本自律神経免疫治療研究会理事長

著者
浜 六郎:医師(内科・疫学)

著者
岡田 正彦:新潟大学名誉教授、医師
本書では徹底して医学論文・学術データにもとづきながら、がん検診の「無効性」「欺瞞性」「危険性」明らかにする。